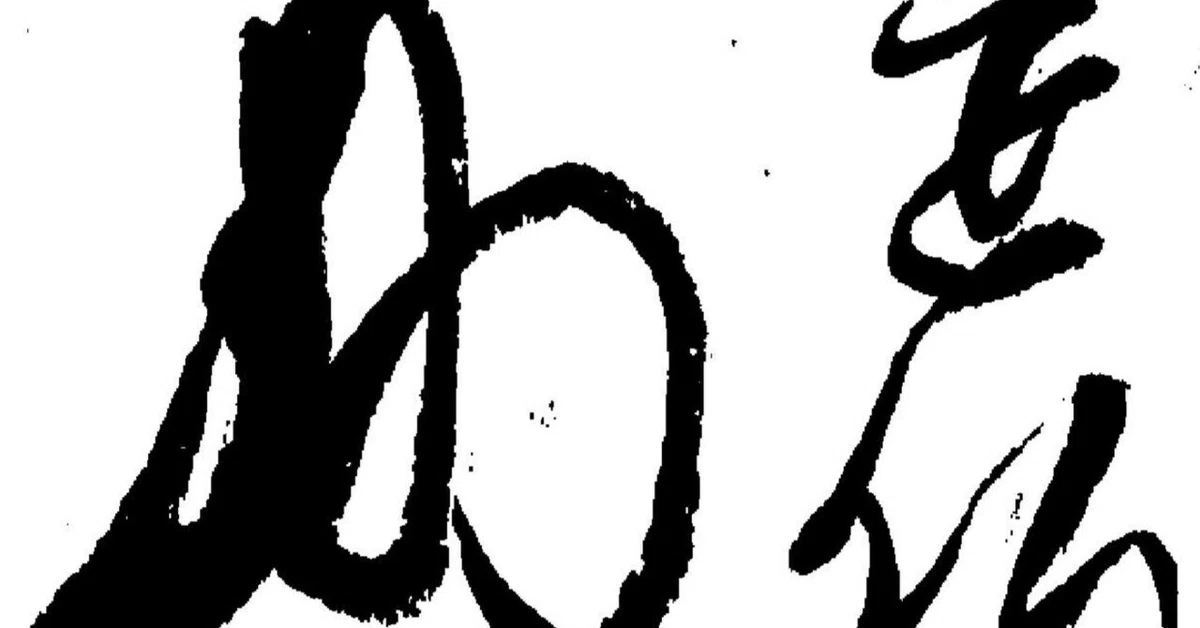島津忠時は、島津家の歴史において、その基盤を固め、発展させる上で重要な役割を担った二代当主です。初代忠久の築いた薩摩・大隅・日向の地頭職や守護職を継承し、さらに鎌倉幕府の中枢で活躍することで、島津氏の地位を不動のものとしました。
島津忠時の概要
その後も穏やかな晩年を過ごし、文永9年(1272年)に71歳で死去しました。
島津忠時の歴史的意義
島津忠時は、単に父の遺産を受け継いだだけでなく、自らの武功と政治的手腕によって、島津氏を鎌倉幕府の有力御家人としての地位に確固たるものにした人物です。特に、在鎌倉での活躍は、地方の武士が中央政界に進出し、その影響力を拡大していく上で重要な意味を持ちました。彼の時代に確立された幕府との関係性は、後の島津氏が室町・戦国時代にかけて九州の雄となるための重要な礎となりました。
生没年: 建仁2年(1202年) – 文永9年(1272年)4月10日(享年71歳)
父: 初代当主・島津忠久
母: 畠山重忠の娘とされる(諸説あり)
通称: 三郎兵衛尉
初名: 忠義
法号: 道仏
墓所: 鹿児島市の本立寺、出水市野田町の感応寺
主要な功績と経歴
承久の乱における武功 (1221年)
後鳥羽上皇が鎌倉幕府に対して挙兵した「承久の乱」において、父・忠久と共に幕府軍として参戦しました。
特に宇治川の合戦では、その武勇を発揮し、7人もの敵将を討ち取るという大きな戦功を挙げました。この功績は『吾妻鏡』にも記されており、幕府方からの高い評価を受けました。
この戦功により、越前国の生部荘(いくべのしょう)と久安保重富(ひさやすのほしげとみ)、伊賀国の長田郷(おさだごう)の地頭職を新たに与えられました。
家督相続と幕府における活躍 (1227年以降)
嘉禄3年(1227年)、父・忠久の死去に伴い、薩摩・大隅・日向の地頭職および守護職を継承し、島津家二代当主となります。
しかし、忠時は父と異なり、基本的に在国せず、鎌倉に常駐して幕府に仕えました。これは、有力御家人として幕政に深く関与し、島津氏のプレゼンスを高めるためと考えられます。
将軍の近習番役(きんじゅうばんやく)に任じられるなど、幕府中枢で重きをなし、その功績として伊賀、讃岐、和泉、越前、近江国内など、各地の地頭職を次々と与えられました。これは、島津氏が南九州だけでなく、全国各地に所領を持つ広域的な武家として成長していく基盤となりました。
文化人としての側面
武人であると同時に、和歌にも造詣が深く、勅撰和歌集である『新後撰和歌集』に2首、『続千載和歌集』に1首の和歌が収められています。これは、当時の武士が単なる武勇だけでなく、教養をも重んじる風潮の中にあったことを示しています。
家督譲渡と晩年 (1265年以降)
文永2年(1265年)、嫡男の久経に家督を譲り、隠居しました。